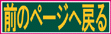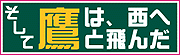
「稀代のクセ者」が、まだアオかったころ
大道 典良外野手

左腕投手から見て「決して長距離砲ではないのだけれど、なぜか苦手で、とにかく対戦したくない右打者」というのは、どこのチームにも1人や2人、いるものです。福岡ダイエーであれば大道選手こそが、まさしくそんな選手なのでありましょう。「あの選手だけは、何を待っているか最後までわからなくて・・・」 痛打された投手は、バックスクリーンに映し出されるリプレイをチラリと見ながら、首をひねります。
そんな、パ・リーグを代表する「稀代のクセ者」も、難波の空の下では、まだまだ「幼鷹」の1人でありました。入団したばかりの「若造」には、まだまだクセ者の匂いなど漂うわけがなく、それこそ必死になって身体を作り、鍛え、1軍選手としての体力と技術力を磨くことが精一杯だったのです。キラキラのドラ1ルーキーだった吉田投手や、即戦力として期待された若井選手に声が掛かることがあっても、当時のホークスには、こんな選手まで1軍で育て続けてくれるだけの余裕などありませんでした。1軍を夢見る若造は、畠山・岸川・永田・山口裕といった、やはり1軍定着を目指すそれぞれのスペシャリストに囲まれながら、必死に自分を作っていたのです。
バッティングもフィールディングも、1軍にはまだまだ遠いものがありました。当時のホークスは、外人選手枠を除くと、佐々木・山本両選手が、外野スタメンをバッチリ握っていましたし、山村・高柳といった「いぶし銀」の選手たちが、いつでも出場できる状態で、1軍ベンチにスタンバイしています。55番という少々大きい背番号も「即戦力」と呼ぶにはかなり厳しいことを物語っていました。
 しかし、この若造には、他の若手選手たちにはない「ガッツ」と「鋭い目」がありました。観客がほとんどいない真昼の大阪球場で、彼は必死にボールを追い、そして戦況を見つめていたのです。時にはフェンスに激突し、担架で運ばれることもありました。でも、そんなことでプレーに「恐れ」が出て、動きが鈍ってしまうようになるほど、この若造の精神力はヤワではありませんでした。
しかし、この若造には、他の若手選手たちにはない「ガッツ」と「鋭い目」がありました。観客がほとんどいない真昼の大阪球場で、彼は必死にボールを追い、そして戦況を見つめていたのです。時にはフェンスに激突し、担架で運ばれることもありました。でも、そんなことでプレーに「恐れ」が出て、動きが鈍ってしまうようになるほど、この若造の精神力はヤワではありませんでした。
「コイツ、もしかしたら上に上がってくるかも知れないね・・・」
「高校出たばっかだから、まだ線は細いけど、面白いかも知れないね・・・」
夕方から始まる1軍戦までの間、ノンビリとバックネット裏に寝転がって2軍戦を眺めている観客にも「若造の鋭い目」には、かすかな期待を感じ取らせるだけの「何か」が光っていたのです。
実際、彼が表舞台に登場するようになったのは、チームが福岡に移ってからでありました。次々と第一線を退く南海選手を後目に活躍を続けさせ、いつしか「クセ者」という絶妙なスパイスをブレンドしてくれたのは、きっと玄界灘の潮風であったのでしょう。しかし、あの確かな技術を支える体力は、だれもいない難波の炎天下で、土まみれになって作り上げられたに違いない・・・。そして、その時の鋭い視線の先には、大歓声に震えるスタジアムがあったに違いない・・・。満員の福岡ドームで、やはり55番を背負い続けながら、大歓声をバックに相手投手をビビらせる「稀代のクセ者」は、その昔、難波のネクスト・バッターズ・サークルでバッティング・グローブをはめながら、ビシッと未来を見据えていたのです。
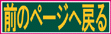
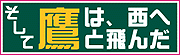

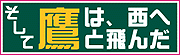

 しかし、この若造には、他の若手選手たちにはない「ガッツ」と「鋭い目」がありました。観客がほとんどいない真昼の大阪球場で、彼は必死にボールを追い、そして戦況を見つめていたのです。時にはフェンスに激突し、担架で運ばれることもありました。でも、そんなことでプレーに「恐れ」が出て、動きが鈍ってしまうようになるほど、この若造の精神力はヤワではありませんでした。
しかし、この若造には、他の若手選手たちにはない「ガッツ」と「鋭い目」がありました。観客がほとんどいない真昼の大阪球場で、彼は必死にボールを追い、そして戦況を見つめていたのです。時にはフェンスに激突し、担架で運ばれることもありました。でも、そんなことでプレーに「恐れ」が出て、動きが鈍ってしまうようになるほど、この若造の精神力はヤワではありませんでした。