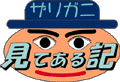 その2:真冬のザリガニを起こしに行こう!
その2:真冬のザリガニを起こしに行こう!
〜 前 編 〜
(平成14年1月1日)
「冬になって、水の温度が冷たくなると、ザリガニは冬眠するのです・・・」 こんなことは、どこの本にも書いてあることですよね。でも、それが、どんな様子で、どう行われているかを実際に見に行くことは、たぶん、ないんじゃないでしょうか? 冬の夜、ある親友とザリガニ談義で盛り上がっていた私は、その時出ていた「冷凍ザリガニ」の話題から、ふと、そんなことに気づいたのです。
「そうだ! こんな寒い日だからこそ、ザリに会いに行こう! 氷の下でじっと春を待っているザリを、ちょっとだけ起こしてみよう!」・・・てなわけで、一面に霜のおりた冬晴れの寒い朝、網を片手に、下駄箱の奥深くに眠っていた長靴を履いて、颯爽と「出撃」したのでした。「南国人」の血をひくこの私にとっちゃ、それこそ拷問のようなこの寒さの中、果たして、お目あてのザリには会えるのでしょうか?


自転車を走らせ、まずはこの春に、若ザリをガンガン釣った「第1ポイント」へ・・・。身を刺すような強いからっ風の中、荒涼とした冬の景色が続きます。同じポイントの「春の風景」が右の写真。基本的な「色」からして、全然違いますモンね(苦笑)。正直、ここに生き物がいるような感じは全くありません。


春ごろ、ここは、右の写真でもおわかりの通り、かなりの水量がありまして、中に入ると、スネの部分まではズブズブと水の中に消えて行くほどでした。ところが、今は左の写真の通り・・・。水量はだいぶ減り、完全に干上がっているところもかなりあります。辛うじて水が残っているところも、氷が張っていたりして、遠くからでは、どこに水があるのか、ほとんどわからない状態でした。この地域は、秋繁殖のアメザリもかなり見られますので、本来であれば、相当数の秋仔が越冬しているはずなのです。果たして、大丈夫なのでしょうか・・・? とても心配なので、まずは水が残っているところを中心に、こうした秋仔の消息を探すことにしました。
 こうして何とか氷が張らずに水が残っているところも、立ち枯れた高草の間に、辛うじて見つけられる程度です。ここも、水深は20センチあるかどうかで、大きさも幅1メートル弱、長さ4〜5メートルといったところ・・・。当然、水の動きもほとんどありませんし、流れもまったく見受けられません。果たして、こんな状態で稚ザリが越冬できるのでしょうか?
こうして何とか氷が張らずに水が残っているところも、立ち枯れた高草の間に、辛うじて見つけられる程度です。ここも、水深は20センチあるかどうかで、大きさも幅1メートル弱、長さ4〜5メートルといったところ・・・。当然、水の動きもほとんどありませんし、流れもまったく見受けられません。果たして、こんな状態で稚ザリが越冬できるのでしょうか?
 水の干上がったところでは、あちこちでこうした「ザリの亡骸」を見ることができます。この写真の個体は、大きさから考えて、だいたい3+くらいでしょうかねぇ。水槽飼育であれば、まだまだ「青年個体」といったところです。やっぱり自然は厳しいんだなぁ・・・。
水の干上がったところでは、あちこちでこうした「ザリの亡骸」を見ることができます。この写真の個体は、大きさから考えて、だいたい3+くらいでしょうかねぇ。水槽飼育であれば、まだまだ「青年個体」といったところです。やっぱり自然は厳しいんだなぁ・・・。
ちなみに、1+以上の個体になりますと、越冬は営巣状態(自分で巣を作って行う方法)が普通です。水中での厳しい環境変化に耐えられない・・・というよりも、やはり巣の中の方が環境面で安定しているからでしょう(これについては、後項で改めて触れます)。となると、「自分で巣を作ることができない個体」というのは圧倒的に厳しいわけで、巣を掘り始める秋口に、第1胸脚のどちらか、あるいは両方が欠損していたりしますと、場合によっては致命傷になる可能性もあるはずです。この個体も第1胸脚が両方ともなくなっていますが、越冬できずに死んで行く個体には、こうした「飼育状態であれば何でもないこと」が原因であることも、決して少なくはないはずなのです。生き物にとっては「当たり前」の光景なのですが、ザリ・キーパーとしては、やはり複雑な気持ちになってしまうものですね。


さっそく水温を測ってみましょう。写真では見づらいかも知れませんが、ここにもうっすらと氷が張っています。観賞魚用水温計を水に浸すこと3分・・・。あれ? 赤い線が伸びてこないぞ? ン? よく見たら仰天! 水温は写真の通り「1度」なのでありました。これじゃあ、伸びてこないハズだよ。氷も張るわけだよなぁ・・・。
 かじかむ両手に気合いを入れて、稚ザリの潜んでいそうな枯れ草の陰に網を入れて行きます。氷のシャリシャリした手応えを感じながら網入れするなんて、生まれて初めて! ほとんど動きのない水の中を丹念に探って歩きます。時折、隣の遊歩道を散歩で通り過ぎる御老人が、不思議そうに立ち止まっては声を掛けてくれまして・・・(苦笑)。そりゃあ、どう考えても怪しい光景だモン。「見てある記」でなく、すっかり「見られある記」状態になっているのでありました。
かじかむ両手に気合いを入れて、稚ザリの潜んでいそうな枯れ草の陰に網を入れて行きます。氷のシャリシャリした手応えを感じながら網入れするなんて、生まれて初めて! ほとんど動きのない水の中を丹念に探って歩きます。時折、隣の遊歩道を散歩で通り過ぎる御老人が、不思議そうに立ち止まっては声を掛けてくれまして・・・(苦笑)。そりゃあ、どう考えても怪しい光景だモン。「見てある記」でなく、すっかり「見られある記」状態になっているのでありました。
 丹念に網入れすること10数回。やっと、稚ザリを発見しました! 体長2センチ前後、完全な今年の秋仔です。やはり、水温が低いからでしょうか? ほとんど仮死状態で、ピクリとも動きません。
丹念に網入れすること10数回。やっと、稚ザリを発見しました! 体長2センチ前後、完全な今年の秋仔です。やはり、水温が低いからでしょうか? ほとんど仮死状態で、ピクリとも動きません。
 「ヤバいことになっちゃったなぁ。やっぱり、掬うんじゃなかったかなぁ・・・」と思いつつ眺めていると、何とかこうして動き出してくれたので、ホッとひと安心。こうして手に持ってから、動き始めるまでには、やはり4〜5秒近くかかりました。動き出してからも、そのスピードは緩慢そのもの。春ごろの機敏さは、カケラも見受けられません。やはり、稚ザリにとっても相当に厳しい状態なのでしょう。水温1度ですから、それも当たり前です。
「ヤバいことになっちゃったなぁ。やっぱり、掬うんじゃなかったかなぁ・・・」と思いつつ眺めていると、何とかこうして動き出してくれたので、ホッとひと安心。こうして手に持ってから、動き始めるまでには、やはり4〜5秒近くかかりました。動き出してからも、そのスピードは緩慢そのもの。春ごろの機敏さは、カケラも見受けられません。やはり、稚ザリにとっても相当に厳しい状態なのでしょう。水温1度ですから、それも当たり前です。
 結局、20分間弱の網入れで、30匹以上の稚ザリを確認することができました。中には、このように「春仔か秋仔か、ギリギリで判別のつかない大きさの稚ザリ」も発見(写真では右上の個体がそれになります。左下の個体は、どう考えても秋仔ですよね!)し、やはり「生後1年未満の個体は、営巣せずに越冬する」ということは、ほぼ間違いなさそうです。確かに、こんな可愛いハサミでは、充分なドロ掘りもできませんものね。
結局、20分間弱の網入れで、30匹以上の稚ザリを確認することができました。中には、このように「春仔か秋仔か、ギリギリで判別のつかない大きさの稚ザリ」も発見(写真では右上の個体がそれになります。左下の個体は、どう考えても秋仔ですよね!)し、やはり「生後1年未満の個体は、営巣せずに越冬する」ということは、ほぼ間違いなさそうです。確かに、こんな可愛いハサミでは、充分なドロ掘りもできませんものね。
なお、今回の網入れで確認した個体は、最も水深の深いとこころにリリースしておきました。これでもって死んでしまうようでは、申し訳が立ちませんから・・・。これらの個体も、上手く育ってさえくれれば、来秋には繁殖に参加できるかも知れません。
ある程度は予想できていましたが、やはり彼らは、非常に厳しい環境の中で、その辛さに耐えながら、懸命に生き抜いています。リリースした後になって、ふと「もし、ここが干上がってしまったら、彼らはやっぱり死んでしまうのだろうか?」という不安が脳裏をよぎりました。確かに干上がっているところは、ほぼ完全な「カラカラ状態」。反面、水があるところには、少ないにせよ相応の量が残っています。これは一体・・・? 不思議に思いながらも探索を続けていた何分か後、意外な事実が待ち受けていたのでありました。成体の巣穴探索を含め、その詳細は中編・後編にて!


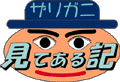 その2:真冬のザリガニを起こしに行こう!
その2:真冬のザリガニを起こしに行こう!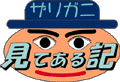 その2:真冬のザリガニを起こしに行こう!
その2:真冬のザリガニを起こしに行こう!



 こうして何とか氷が張らずに水が残っているところも、立ち枯れた高草の間に、辛うじて見つけられる程度です。ここも、水深は20センチあるかどうかで、大きさも幅1メートル弱、長さ4〜5メートルといったところ・・・。当然、水の動きもほとんどありませんし、流れもまったく見受けられません。果たして、こんな状態で稚ザリが越冬できるのでしょうか?
こうして何とか氷が張らずに水が残っているところも、立ち枯れた高草の間に、辛うじて見つけられる程度です。ここも、水深は20センチあるかどうかで、大きさも幅1メートル弱、長さ4〜5メートルといったところ・・・。当然、水の動きもほとんどありませんし、流れもまったく見受けられません。果たして、こんな状態で稚ザリが越冬できるのでしょうか? 水の干上がったところでは、あちこちでこうした「ザリの亡骸」を見ることができます。この写真の個体は、大きさから考えて、だいたい3+くらいでしょうかねぇ。水槽飼育であれば、まだまだ「青年個体」といったところです。やっぱり自然は厳しいんだなぁ・・・。
水の干上がったところでは、あちこちでこうした「ザリの亡骸」を見ることができます。この写真の個体は、大きさから考えて、だいたい3+くらいでしょうかねぇ。水槽飼育であれば、まだまだ「青年個体」といったところです。やっぱり自然は厳しいんだなぁ・・・。

 かじかむ両手に気合いを入れて、稚ザリの潜んでいそうな枯れ草の陰に網を入れて行きます。氷のシャリシャリした手応えを感じながら網入れするなんて、生まれて初めて! ほとんど動きのない水の中を丹念に探って歩きます。時折、隣の遊歩道を散歩で通り過ぎる御老人が、不思議そうに立ち止まっては声を掛けてくれまして・・・(苦笑)。そりゃあ、どう考えても怪しい光景だモン。「見てある記」でなく、すっかり「見られある記」状態になっているのでありました。
かじかむ両手に気合いを入れて、稚ザリの潜んでいそうな枯れ草の陰に網を入れて行きます。氷のシャリシャリした手応えを感じながら網入れするなんて、生まれて初めて! ほとんど動きのない水の中を丹念に探って歩きます。時折、隣の遊歩道を散歩で通り過ぎる御老人が、不思議そうに立ち止まっては声を掛けてくれまして・・・(苦笑)。そりゃあ、どう考えても怪しい光景だモン。「見てある記」でなく、すっかり「見られある記」状態になっているのでありました。 丹念に網入れすること10数回。やっと、稚ザリを発見しました! 体長2センチ前後、完全な今年の秋仔です。やはり、水温が低いからでしょうか? ほとんど仮死状態で、ピクリとも動きません。
丹念に網入れすること10数回。やっと、稚ザリを発見しました! 体長2センチ前後、完全な今年の秋仔です。やはり、水温が低いからでしょうか? ほとんど仮死状態で、ピクリとも動きません。 「ヤバいことになっちゃったなぁ。やっぱり、掬うんじゃなかったかなぁ・・・」と思いつつ眺めていると、何とかこうして動き出してくれたので、ホッとひと安心。こうして手に持ってから、動き始めるまでには、やはり4〜5秒近くかかりました。動き出してからも、そのスピードは緩慢そのもの。春ごろの機敏さは、カケラも見受けられません。やはり、稚ザリにとっても相当に厳しい状態なのでしょう。水温1度ですから、それも当たり前です。
「ヤバいことになっちゃったなぁ。やっぱり、掬うんじゃなかったかなぁ・・・」と思いつつ眺めていると、何とかこうして動き出してくれたので、ホッとひと安心。こうして手に持ってから、動き始めるまでには、やはり4〜5秒近くかかりました。動き出してからも、そのスピードは緩慢そのもの。春ごろの機敏さは、カケラも見受けられません。やはり、稚ザリにとっても相当に厳しい状態なのでしょう。水温1度ですから、それも当たり前です。 結局、20分間弱の網入れで、30匹以上の稚ザリを確認することができました。中には、このように「春仔か秋仔か、ギリギリで判別のつかない大きさの稚ザリ」も発見(写真では右上の個体がそれになります。左下の個体は、どう考えても秋仔ですよね!)し、やはり「生後1年未満の個体は、営巣せずに越冬する」ということは、ほぼ間違いなさそうです。確かに、こんな可愛いハサミでは、充分なドロ掘りもできませんものね。
結局、20分間弱の網入れで、30匹以上の稚ザリを確認することができました。中には、このように「春仔か秋仔か、ギリギリで判別のつかない大きさの稚ザリ」も発見(写真では右上の個体がそれになります。左下の個体は、どう考えても秋仔ですよね!)し、やはり「生後1年未満の個体は、営巣せずに越冬する」ということは、ほぼ間違いなさそうです。確かに、こんな可愛いハサミでは、充分なドロ掘りもできませんものね。